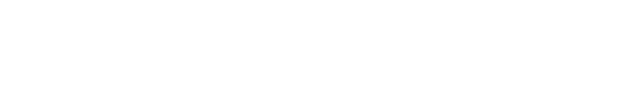腹膜透析について
腹膜透析について
腹膜透析(Peritoneal Dialysis=PD)は、おなかに透析液を出し入れし、自分の『腹膜』を利用して体の余分な水分や老廃物を取り除く治療法です。
我が国では80歳以上の高齢透析患者数は年々増加傾向であり、2021年12月末時点で77871人、全透析患者の23.1%を占めています。
80歳以上では透析導入後1年以内に30.2%が死亡、平均余命は男性4.8年、女性5.6年と報告されています。
そのような中、日本では多くの高齢血液透析患者さんは週3回の通院負担、透析後の血圧低下、倦怠感、認知症の進行、通院困難になると社会的入院が必要になる方が大半であり、高齢化の進行により透析により元気に社会復帰するというより透析により生かされている、透析自体が延命治療となっている側面が強くなっています。
このような高齢透析患者の現状を解決するために当院では地域社会資源(訪問看護師やデイサービス、有料老人ホームなど)と連携した緩和的腹膜透析療法に積極的に取り組んでいます。
緩和的腹膜透析とは治療優先の透析ではなく、透析交換回数を限りなく減らし(1日1~2回交換以内)、患者本人はもとより介護する家族の身体的・精神的負担軽減を行うことで、自由で高い生活の質(QOL)の維持が期待できます。
また、当院では通院が困難となった時点で訪問診療も可能であり、最期まで在宅や施設で過ごすことで腹膜透析を継続しながら穏やかな終末期を過ごし、自然な死(老衰)が迎えられるようにサポートを行います。
療法選択外来について
末期腎不全(eGFR15未満)で近い将来透析が必要と言われた方に対して医師・看護師・ソーシャルワーカー・(必要により訪問看護師・ケアマネジャー)など多職種で療法選択(腎臓移植・腹膜透析・血液透析・保存的腎臓療法:透析をしない選択)説明を行います。
―腎臓移植を希望される場合は、移植可能施設へ診療情報提供書を作成し、透析開始前に移植を行う先行的腎臓移植をお勧めします。
―腹膜透析に関しては手術前からバッグ交換の手技指導・訪問看護師と連携した自宅訪問・環境整備・導入後の継続した在宅支援(訪問看護師+当院在宅支援部)を行います。特に高齢者で入院による認知症の進行、筋力低下が危惧される場合は可能な限り入院期間の短縮(最短2泊3日)を行い、ご自宅での訪問看護師のサポートによる導入(アシストPD)を行います。
―血液透析を希望される場合は近隣の医療機関に診療情報提供書を作成し、内シャント造設をお願いし、適切な時期に透析の開始ができるようにサポートします。(維持血液透析は当院では対応しておりませんので近隣の医療機関へ転院して頂きます。)
―現在血液透析中の方で週3回の通院が負担に感じている、倦怠感に悩まされている等ある場合は腹膜透析の併用療法に移行することで解決する可能性もあります。
その場合血液透析(週1回)は現在通院中の医療機関で継続、腹膜透析は当院へ月1~2回の通院となります。
併用療法へ変更後に血液透析施設への通院が困難となった場合は腹膜透析単独療法へ切り替え、訪問診療での対応も可能です。
まずは現在の担当医と相談上、希望される場合は当院在宅支援部(093-863-1211)までご連絡ください。
腹膜透析での連携病院・クリニック・施設・訪問看護ステーション(ST)
産業医科大学病院 小倉記念病院 済生会八幡病院 JCHO九州病院 田川市立病院 新中間病院 製鉄記念八幡病院
今村クリニック 有料老人ホームコピーヌ中間 生協ホーム赤とんぼ
すずらん訪問看護ST 訪問看護STよりそい 在宅看護センター北九州 訪問看護STきのこハウス